これからの酒づくりを考えるにあたり、蔵元がいま会いたい人たちとお酒を酌み交わしながらお話を伺うこの企画、2回目はライターの藤田千恵子さんをお招きします。今回は蔵人の食を預かる山根明子もお話に加わりました。
純米酒の復興期に日本酒に出会い、以来、言葉によって酒づくりの現場に伴走してきた藤田さんは日本酒ライターの先駆けともいわれますが、同時代をともにした蔵元にとっては“戦場カメラマン”のような存在でした。
戦時の米不足を背景にアルコール添加酒が広く普及していた1970年代、純米酒を造ることは、今では考えられないような「常識」との闘いでした。
「日本酒の戦後を終わらせたい」と願い、純米酒だけを醸造する全量純米蔵への復帰を初めて実現したのが昨年4月に逝去した神亀酒造蔵元・小川原良征さんです。自蔵の酒造りの時期であっても全国の蔵元の応援にかけつけて、惜しみなく醸造の知識を提供、共有し、各地に純米酒を根づかせた小川原さん。その酒づくりを1980年代中期から藤田さんは見つめてきました。
今宵のテーマは「物に命が宿るとき」。小川原さんはなぜ多くの反対にあいながら自らの信じる酒を造ることができたのか。純米酒復興の道のりをふりかえりながら、物づくりに宿る命を言葉で表してきた藤田さんと、その原点を考えます。
第2回(中編)は書き手としての藤田さんのお仕事の「うしろがわ」を伺います。
[2017年6月収録(18年6月追加収録)|全3回掲載]

ゲスト:藤田千恵子(ふじた・ちえこ)さん
ライター。酒と醗酵食を中心に日本の食と生産者を捉えた数々のフードライティングを発表。雑誌寄稿多数。日本酒の魅力を発信するだけでなく、同時代の酒造りに携わる多くの人々を鼓舞してきた。著書に『愛は下剋上』(NTT出版/ちくま文庫、1992年)『日本の大吟醸100』(2001年)『杜氏という仕事』(ともに新潮社、2004年)、『これさえあれば―極上の調味料を求めて』(文藝春秋、2006年)、『美酒の設計』(マガジンハウス、2009年)など。現在『あまから手帖』に「イッポン!」、『住む』に「蔵のたからもの」連載中。2004年より長野県原産地呼称管理制度日本酒官能審査員。日本の醗酵食品と日本酒を共に味わう「醗酵リンク」主宰。
〈醗酵リンク〉––日本酒を飲んでほしかった
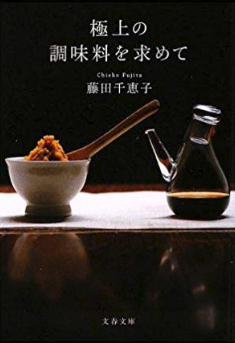
明子:千恵子さんは、2001年に「醗酵リンク」という活動をはじめられ、お醤油や味噌の生産者を訪ねた御本もありますが(『極上の調味料を求めて』)、調味料に興味をもたれたのはいつ頃からなんですか?
藤田:20代の頃にセンム(神亀酒造7代目蔵元・小川原良征氏|前編参照)から教わったのが最初ですね。センムにいわれた通りのお醤油屋さんにもお味噌屋さんにもすぐに出かけていって。その頃はセンムもあまり忙しくなくて、神亀のお酒をお土産に持ってきてくれて一緒に取材に行ったり。その後、十年以上経ってから、子どもが生まれて保育園に預けて仕事をしてという頃に、やっぱりごはんってとにかく大事だなと、改めて考えるように。そのときに、忙しいときこそ、良い調味料が味方になってくれると気がつきました。
山枡さん(山枡酒店店主・山枡俊二さん)が「どんなにいい酒を飲んでも、化学調味料を使ったものを食べると口のなかで三増酒ができる」という名言を発していて、ほんとに「うまいこと言うな」と思いました。「これだけいいお酒を飲んでいるんだから、食もちゃんと吊り合いがとれないといけないな」とはかなり早い時期に思ってたんですが、そうはいっても自分が忙しくて手をかけられないときもある。でも、素材の良いものを買って、きちんとした調味料を使えば、おいしくて体に良い食事はすぐできちゃう。ほんと楽だなと思いました。
明子:グルメに走るという意味ではなくて、粗食であっても食と酒の格があうと、どちらかひとつだけでは味わえない幸せを感じるところは確かにありますね。そして、忙しい人ほどちゃんとした調味料を使ったほうがいいということも、私も自分の暮らしのなかで実感しています。出汁だって、日本の出汁ほど簡単にとれるものはないです。
藤田:そうそう。世界最速の出汁だから。一週間、牛を煮込んだりしなくていいもの。みんな〝ファーストフード〟っていうとハンバーガーを連想しがちですが、どうして「味噌のおにぎり」をファーストフードにしないんだ、と。いまようやくおにぎり屋さんも増えましたけど、遠い国から海を渡ってきた牛肉を使って、それで「ファーストフードいうな!」って思っていました。
明子:それがまさに『極上の調味料を求めて』の最初のところで書かれている「身近なものに興味がわかず、尊敬を払いにくいのは、家族という例をとってみてもわかる人間のサガではあるが、ここは、ひとつ、身近な調味料をきちんと見直してみたい」(「はじめに」)というところに結びつきます。本当にそうですよね。
藤田:ほんとにそう。食べ物だけでなく暮らし方や畳なんかもそうですが、日本人の暮らし方というのは、お金のあるなしに関係なく、体を整えやすいと思うんです。以前、合気道を習っていたときに、その先生が「人間は、畳に正座するだけで体が整う」と。やっぱり、日本には身体性の高い文化があるのだと思います。
明子:着物にしても、体を筒状に包むから体幹が整うといいますものね。私自身も、最近改めて思うのは、自分は日本人なのに日本のことをまだまだ何も知らないなと言うことだったりしますが。現代の日本人の生活のなかから、どんどん「日本らしさ」みたいな美意識が消えていっていることは感じます。
藤田:食べることも暮らすことも身体意識として高いものがあるはずなのに、現在では、あまり使われていないな……と。〝発酵〟もそうでした。
明子:いまはあちこちで「発酵ブーム」なんて言われてますけど、ブームと言われ出したのはそんなに前からではないですよね。千恵子さんが「醗酵リンク」を始められたのは2001年。早いですね。どうして始めようと思われたんですか。
藤田:「醗酵リンク」を始めようと思ったのは、まずは日本酒を飲んでほしかったから。そのころは消費低迷期でしたから。日本酒を飲んでもらうには、食との連携が不可欠で、食卓が整わなければ、日本酒には手が伸びないだろうと。で、その食卓を手軽に整えるためには、良い調味料が必要だと思いました。その調味料の魅力を知って貰うには、日本酒の力がいる。日本酒の力を借りて、互いに補い合ってほかの発酵調味料にも目を向けて貰おうと思ったんです。
たとえば、蔵元の山根さんが東京に出てきたら「山根さんを囲む会」がひらけますよね。でも調味料の社長さんが東京に出てこられて囲む会ができるかというと、なかなか難しい。だからやっぱり、味噌や醤油やお酢、すでに日本にある良いものを知ってもらうには、絶対日本酒の力を借りようと思ったんです。それで「お酒の会」のスタイルをとって、たとえば神亀さんだったらブースを北海道の共働学舎のラクレットチーズの横に出してもらうとか、竹鶴さんだったら、醤油と腐乳で煮込んだ豚の角煮のブースの隣に立ってもらったりですとか。調味料の魅力が引き立つように、日本酒と相性の良い料理を組み合わせて。
日本酒の世界は当時は地味に思われているようでしたけど、実は熱心なファンは多くて、発酵の世界の花形なんです。だから〝日本酒〟と言ったら人は集まってくれる。会場には、フランク・ロイド・ライトが設計した自由学園という小学校をお借りしました。小学校ならば給食室を借りて、火を使うこともできる。それで「ヨシッ!」と思って。建築物が美しいから、それを見るためだけでも、来てくれる人が増えるかもしれないし。
明子:その辺りの組み合わせが千恵子さんはとてもお上手だなと思います。人が「おっ! これはなにか面白そうだぞ!」と思うように、いくつか魅力的なものをかけ合わせて仕組みを考えられるじゃないですか。
藤田:良いことでも悪いことでも、物事が起きるときというのは、いくつかのことが重なるときですね。それで「醗酵リンク」のときも、何かと何かを組み合わせる、というような工夫をしました。そのときもその企画を小川原センムにお話したら、「ぜひやれやれ」と言ってくれて。「俺はなぁ、お前が儲けようとしてねーから応援するんだよ」と言って、ごっそりと、会が終わったあとも人に配れるくらいたくさんのお酒を運んできてくれました。嬉しかったですね、応援して下さるお気持ちが。
「おいしい」のうしろがわ––手順にあらわれるもの

藤田:「日本のファーストフード」がすごいと思うのは、使う側にとってはファーストであっても造って下さっている側は決してファーストではないからなんですよね。お味噌だってお醤油だって、ものすごい時間をかけて造られているから、使用する際にファーストフードとして成立するのであって。
明子:誰かが面倒くさいを引き受けてくれているから、食べる人が楽ができる。
藤田:お酒や醸造物を造る手順は、それを文章にすると長くなってしまって、「読者はそこまで興味ないですよ」と言われることもあります。でも、たとえば杜氏集団だとか、あの寡黙な人たちが「どんな気持ちでものづくりをしているか」ということは、自分から話す人たちではないですから、どこまで手をかけているか、その手順を追わせてもらうことでしか伝わらないところがあるのではないかと思うんです。それで、その手順を追いかけたくなる。
明子:『極上の調味料を求めて』は、醤油、お酢、塩、味噌、ポン酢、鰹節、みりん、それからごま油、全国の津々浦々の醸す人をたずねてますね。「手順」のドキュメントになっている。
藤田:手順というのは「どんな蒸気でどのくらい蒸すのか」とか「どうして機械で冷却しないのか」とか……全部やはり「どういうものを造りたいと思ってそれをしているのか」ということで、「これはね」なんて言葉で言いながら体を動かしているわけではないですね。その人たちが目指してるもの、着地したいこと、「こういうものを造りたい」と目指すものというのは、その合間合間の仕事に表れているんだと思うんです。もっとさかのぼれば、どういうお米や大豆を使いたいと思っているかも含めて。
たとえば、原料を受け取りに行くときに「精魂込めてつくってもらってる農作物を宅急便で送ってもらう気にはとてもなれないから」と遠くまで自分で車で運転して取りに行くお味噌屋さんもいる。でも、宅急便でも車で行っても、原料の成分は変わらないじゃないですか。でもその人はそういうことばっかりしてる。「なんで運転してまで行くのか」といったら、農家さんを直接訪ねていってお礼も言いたいのだろうし、たぶん、その人、そういう風に生きていきたいということなのかなと。ちゃんと栽培してくれた人の顔見て受け取りたい。たぶん胸に押しいだくように材料を扱うのだろうなって。
明子:ああ、それは山根酒造場がお世話になってる酒米の契約農家さんのところに伺っても思います。田んぼの除草作業ひとつをとっても、極力、薬を使わずなるべく人力でとなると、ほんと見ていても気が遠くなるような作業で。田んぼだって当然ひとつやふたつでなく、車で移動しながらいくつも面倒みないといけないのに。これをたった家族3人と繁忙期に外部でひとりふたりの助っ人をお願いするだけで回しておられるのかと思うと、本当に頭が下がります。草って抜いても抜いても、またどんどん生えてくるでしょう? それでも「地道に当たり前のことをするのが大事だからね」って。その言葉の重さみたいなものをすごく感じました。
藤田:それで分量も採れないですからね。
明子:ある酒米農家さんに「欲張って量をとろうと思えば蔵に求められている米とは作り方も変わってしまう。だから、うちはそういうことはせんよ」って、言われたのを聞いたとき。酒蔵と農家が本当に同じ目標に向かっていこうという信頼関係がないとなりたたないことだなと思いました。
藤田:目指すものの方向を理解しあっておられるんですね。どんなものを造っていきたいのか、という思いは、造る過程に表れますね。淡路島で、ひとりで魚醤を造っているかたのこと思い出しました。その方も、漏斗で魚醤をビンに手で詰めて、お湯沸かして加熱して品質の安定のために殺菌したりして。そんなの機械でさっとできる工場が多いなかで、その人はその仕事をひとりで続けているのだけれど……。こういう人がいるんだな、そういう人を「地の塩」というのではないかと。
光の仕事 陰の仕事––書くことで伝えたいこと

藤田:その魚醤は、仕込んで一年経ったら発酵だけなら終了するんです。でも、その人は「塩角(しおかど)が取れないから」というので3年寝かせる。「塩角なんて言葉、今はあまり使われないんじゃ……」とも思うけど、もう彼はほんとに「奥の細道」というか、発酵の細道みたいな奥の奥の丁寧なことをやっていて、なおかつ語らないものだから、せっかく良いものを造っていても、知られざる銘品みたいなことになってしまう。私だって、その生産者さんのことは、編集者の方に教えて貰って知ったわけですが。
味わってみたら、奥深い旨みがあって、汁物も煮物もグンと美味しくなる。添加物も使用されてない。魚醤は手のかかる希少なものでしょう。それを一人で造っておられる人かいるんだなあと思って、そのことを原稿に書かせてもらったのですが、あとでご本人に原稿をチェックしてもらった際に、編集担当の方に「よすぎるっていうか……なんていうのか、いいんですかねぇ、こんなに(書いて貰って)……」ってぽそぽそって言ってくださったそうなんです。あくまでそういう謙虚な人というのでしょうか、そういうことを口で主張する、というような生き方ではないというか。
明子:千恵子さんは、そうやってモノづくりの現場のなかなか光のあたらない場所に自らが切り込んでいかれることで、言葉の力でエールを送り続けてくださってます。「この人がこんな風にわかってくれているなら、自分のこれまでの影の苦労も報われる」そんな気持ちになったかたが、きっとたくさんおられるはずです。私自身も、今まで千恵子さんの言葉にはずいぶん助けられてきました。
いまの私は、外で個人として食の仕事をしながら、まかないですとか蔵の仕事もすることで、半分内側から、そして半分外側から関わっているような状態です。立ち位置は千恵子さんとは異なるのですが、伝えることの難しさはいつも強く感じています。
蔵の仕事は一般の方から見ればわからないことが多くて当然じゃないかと思うんです。私自身も、中に入ってみて、こういうことなのかと初めて知ることの連続ですし。だから伝える努力をしないで「周りがわかってくれない」というのも違うと思う。
かといって、自分が伝えようとすればすぐ伝わるかといったら、そんな簡単なものでもないですね。伝わらないと悲しいけど、伝えるってそもそも誰にとっても難しいことです。時間がかかって当たり前というくらいの気持ちで、まずは自分が楽しみながら、内側からも発信し続けるしかないのかな......と思ってます。
藤田:光があたって、初めてその仕事の価値がわかるということではなくて、この世がそのような地の塩のような仕事によって成り立っている、光の仕事の背後に陰の仕事があるということがね、想像してもらえるようになったらいいな、と思いますね。
今は好景気だという見方もあるけど、私は製造の現場では実は不況なんじゃないかなと感じています。私の尊敬している人たちのなかでも、仕事で難しい局面に来ていて、懸命にやってきても閉めていかなきゃいけない人も出てきている。私の定義ではありますが、「不況って何か」というと、お金のことが原因で何か大切なことや丁寧な仕事をあきらめなければいけないということで。
明子:ああ……。
『極上の調味料』の「あとがき」のなかで「醸す、ということは、操作ではなく、生きものの世話をすること」っていう坂巻醤油の坂巻弘道さんのお話を書いておられますよね。うちの社長も「酒造りとは本来、微生物のペースに人間が合わせるもんだ。人間の都合にあわせて、それらを無理矢理コントロールした酒はそれなりの味がする」って言っていて。それまで、自分は人間同士でスケジュールをきっちり組んで、それに従って仕事を進めるのが当たり前というやり方で人生のほとんどを生きてきたので「なんとそんな世界があるのか!」と目からウロコが落ちる思いがしました。熟成ということにしても、うちのお酒は春にしぼった酒をすぐに出すというよりも、時間をかけて寝かせることで目指す味になっていくタイプのものも多いんですね。当然、資金繰りを優先させればすぐに販売できるお酒のほうがいいのだろうけど、お金の事情でまだ納得いかない状態のものを早く出荷するわけにもいかないでしょうし。待つのも仕事というか、人間は見守り役なのだなと思います。
藤田:そうなのでしょうね。お酒造りというのは、米という固体が液体になるまでの仕事ですよね。液体になるまで「その米がどういう道順をたどるか」は蔵それぞれじゃないですか。もっとさかのぼれば、どういうお米を作るのか、農家さんひとりひとりとどんなやりとりをするのか、ですとか。
でも考えてみたら、原料のお米の差は、飲む人の目に見えるわけじゃない。なんでもお酒になると考える人もいるかもしれないけれど、でも「そうじゃない」と思って選り抜きのものを求める人もいるわけで。だから……多分どういう生き方をしたいかということでもあるんだろうなぁと思うんですよね。ほんとに何に向かって、どういう仕事するのかって––その人がどういう風に暮らしていきたいか、ということなんでしょうね。
明子:きれいごとじゃなくて、自然環境とか、どういう地球をこの先残していきたいかも含めて。
藤田:東日本大震災の後にも、そのことを思わないではいられませんでした。原発事故が起きたあと、自然食品系のお店に商品を卸していた東北や関東の生産者の人たちは、お店側が食品を選ぶ基準が高かったために、今まで「安全な食品を」という高い意識でむすばれていた絆が、反対に切れてしまった。今までのように安全だとは思って貰えない生産地で、ものづくりを続けなければならない人たちは、かなりきつい状態だったようなんですね。その人たちはサイレントマジョリティーというのかな、声高に何かを言ったりしてるわけではなかったけれど、見えないところにたくさんいたと思うんです。
そういうことを経てきている方々のご苦労を見聞きしていると、生きるって抗うことだなって。流れのままに生きるというのも生きることだし、だけど「いやそうじゃないんだよな」と思って抗うことも生きることだし。私の仕事は、そういうお蔵の方々、生産者の方々の取材をさせて頂くことも多かった30年だったと思います。
命の世話にかかる時間

藤田:なので、そういうことを経て出来上がってきているものに対して、つまりは生産者さんたちの仕事に対しては、とにかくきちんとした対価を払いましょうよ、と思います。お味噌もお醤油もお酢も、再生産を続けて貰えるような金額を消費者の側も支払わなければと。「そうしないと、造って貰えなくなる。大切なものがなくなってしまう」という危機感を感じます。たとえば駅前のホテルで人と打ち合わせするとき、コーヒーには800円払うのに、なんで800円のポン酢のことは高いと感じてしまうのか。ポン酢はスーパーで198円で買えると思っている人も多いけど、そもそも日本の調味料は安すぎるんです。
明子:たしかに不思議とそのときだけのことにはお金を払っても、使いこなせばしばらく楽しめるものに日本人って意外とお金を払わないですよね。でもそれって、社会全体の余裕のなさというか、自分を世話する時間とか、外には見えない内側を満たすことを後回しにしがちな世の中だからというのもあるのかな、と。
そもそも人間が生きていくっていうことって、死ぬまでの世話を焼くということがすごく大切な仕事のはずなのに、そこに金銭が発生しないと急に馬鹿にするというか、価値の低いことに思ってしまうところはあるのかもしれません。でもその構造自体がもう限界がきていて、すでに破綻しているんじゃないかなとも思います。
今の世の中で働いてると、自分の命の世話をするってことがほんとにぎりぎりのところがある。個人のある程度ゆっくりした時間がないと、「おいしい」とか「まずい」とかいう感覚もだんだんわからなくなってきます。食事って日々のことだから、いっつも頑張るのは大変ですし、今日はもうなんにもしたくないってときもありますよね。私もけっこうあります(笑)
でも男も女もごちそうでなくとも、自分が食べるごはんくらいは作れたほうがいいと思うのは、自分の本能や感覚に従った食事の支度を最低限はできることって、一生の財産になると思うからです。食べるということを自分の手に取り戻す。そこをすべて人まかせにしてしまうと、誰もが本当はもっているはずの野生のセンサーみたいなものが鈍って、本来進んでいきたい生き方の方向もわからなくなっていってしまうんじゃないか? そんな気がするので。
藤田:「醗酵リンク」を開催してから17年たちましたが、発端としては子供が20歳になったときに、成人式には日本酒で乾杯してほしいという気持ちもあったんです。そのためには、きちんとしたものを食べさせて育て、心身とともに舌の感覚も守らなければ、日本酒には手を伸ばさないだろうと。20歳になって、いきなり日本酒を飲んでもらえるわけではない。そこにいたるまでに日本酒を飲みたいと思う食卓を見せて育てないと、って。飲んでる姿だけは、たくさん見せてますけど……(笑)
明子:千恵子さんは以前から、日本酒のような複雑で繊細な味覚を拾えるようになるには、食と両輪で子どもの頃から時間をかけて舌を育てていかないとなかなか難しいということを、ずっと言われてきましたものね。17年前に、そういうふうに考えられてたのか……。
藤田:保育園からの帰り道、ごく普通に外食をしようとすると、その大半に化学調味料が使用されている。それが普通のことになっているのでは、こどもたちの舌はどうなるのかなと思いました。でもやっぱりその当時よりも、さらに食の環境を守るということや、生産者を買い支えることというのは、現在のほうが意志の必要なものになっていますね。世の中の人たちの財布のひもが固くなっていることでコストを抑えた食材や食事もさらに増えている。自分が歳をとったということもありますが、ちゃんと食べる、ちゃんと食べさせるというのは大変なことだなって。やはり意志が要りますね。
「酒は全てを正す」––自分の基準を日本酒に合わせたかった

藤田:でもどうしてそういうふうに食全般に興味を持ったかというと、小川原センムの道案内も含めて、日本酒に出会ったからです。私は本も映画も旅も好きだけど、自分をまともにしてくれたのは日本酒でした。この日本酒にふさわしい私になりたいなぁと思ったんです。飲酒自体をまともじゃないと思ってる人もいるかもしれないけど。いまの自分が20代の自分を思い返したときに、バカ者なりにまともなことがふたつあって、ひとつは自分の基準を日本酒に合わせたいと願ったこと、あと仕事では日本酒の専門誌以外で原稿を書こうと。
明子:それをもう20代のときに意識しておられたとは!
藤田:日本酒の業界誌でアルバイトしてたときに、その雑誌の存続は蔵元さんたちの広告費にかかっていると気づきました。なので、自由にものを書くためには、お蔵には自分がよそで働いたお金でいこうと。
日本酒に合わせたいと願ったのは、自分の暮らしの中で一番グレードが高かったのが日本酒だったからです。日本酒を飲むようになったら、まずは食べ物が変わるでしょう。「酒はすべてを正す」––食べ物が変わってきたら、それにつれて器も変わる。着物も着たくなる。日本酒を飲んで、日本人ってすごいなと気づかされました。
私が中学生くらいだった頃から、なんとなく、日本人は世界で嫌われてるのかな、みたいな空気を感じることがあって。エコノミック・アニマルなんて言葉もあったし、もう少し大人になってからも日本車がアメリカで燃やされてしまったり、日本企業は嫌われているのかなあ、なんて感じることも少なくなかった。それで、自分が日本人だということにあまり誇りも持てなかった頃に、人の造ったもので自信を持つのもおかしいけど、いや日本酒があるじゃないか!と思えたんですよね。「日本人はすごい」と思えた最初のきっかけが日本酒だった。ほかの何よりも日本酒が先でした。
民族としての誇りや肯定感って、戦争に負けてからは当然のことながら、強くは持てなかったろうと想像します。その世代の親に育てられた私もまた、日本人ということに自信は持てていませんでした。でも日本酒を飲むようになって、素晴らしい醸造法の現場を見せてもらうようになった時には「日本には日本酒があるじゃないか!」と思いました。
だから当時はまだまだ日本酒をとりまく環境は厳しい時代だったと思うんですけど、とある蔵元さんに「蔵元さんっていうのはお酒を飲む人間からしたら憧れの存在なんですよ」といったら、その人「はぁー」ってキョトンとされて。でも蔵元には選ばれた人しかなれないと思うんですね。「大きくなったら俺パン屋になる」という人はいるかもしれないし、なれるかもしれないけど、「俺大きくなったら蔵元になる」とはなかなか言えない。水、人材、環境に恵まれたところでないと蔵を建てることは難しいですし。
明子:どの家に生まれるかも自分でコントロールできることじゃないですもんね。宿命的なものというか。それを否定的にとらえれば、継がなきゃ仕方がなかったということにもなるけれど。でも、考えようによってはすごく選ばれている。個人的には、これからは必ずしも血縁に限らずとも、酒造りの志を同じくする人が継げるような世の中になるといいなとは思います。ただ酒蔵って代々続いているだけに、光の部分だけでなく、多分に負の遺産といった影の部分も合わせ持っていると思うので、いいとこ取りでなく全てを引き受けるとなると、双方ともにかなりの覚悟がいることだとも思います。
藤田:大分県に「鷹来屋」(たかぎや)というこれも大好きなお酒があるのですが、そのお蔵は、酒米も栽培されて農業も醸造業も共にされているんですね。現在の蔵元さんは、中学生のころに、杜氏さんが来られなくなったり、ご家族が病気になられたりで、親御さんが一度蔵を閉められたそうです。なので生家は酒蔵なのに、酒蔵を継げなかった。大学を卒業してからは全然違う業界の営業マンになって、でもお酒が好きで、酒蔵をいつか復活させたいと願いながら、通信教育で醸造を学んでいたそうなんです。その苦労されてた時代を奥さんがずっと見てらしたのですが、「俺は日本酒がこんなに大好きなのに、なんでお酒が造れないんだ、といいながら、いつも彼はお酒を飲んでました」と。そうやって悔しい思いやご苦労もあって、お金も工面されて、いまは農業からやっておられるんだけど、その方は、自分の息子さんが「土下座して継がせてくださいっていうまで継がせない」って。それくらい自分にとって酒蔵を立て直すまで強い思いがあったということでしょう。だから復活して最初にできたお酒を飲んだときに、彼は「もう死んでもいい」って言ったそうです。そこで奥さんが「死なないで、売らなアカンよー」って言ったって。
明子:素晴らしい!(笑)
藤田:酒蔵の奥さんには、女傑が多いですね。その奥様もお料理が上手で、お蔵を訪問した時に、ご馳走をたくさん出してくださって。馬刺がすごい新鮮ですねって言ったら「そうですよ、さっきまでヒヒンって鳴いてました」って(笑)
満たされるとは

藤田:とにかく私が口にしてきたなかで一番グレードの高いものって日本酒だったわけですよね。育ってくる過程で、そこまでグレードの高いものは口にしないで生きてきて。
20代でそれほどお金ももってないときに、身分不相応に飲めたのが、いい日本酒だったわけです。そうすると、たぶん人間は、そこまで素晴らしいものを飲ませて貰ったら、あとのものも譲れなくなってくる。〝わーっ〟と吟醸だけ飲んで、そのあとファーストフード店には入らない。やっぱり人間の体ってかしこくて、いいものが入ると全部上がると思うんです。
明子:たしかに、この間、外でおいしいお蕎麦とお酒を頂いたときに、量はそれほど食べてなかったんですが、なんだかとても気持ちが満たされたんですね。そのとき社長が「ああ、このあともう余計なもの入れたくないな」って隣りで言ってて、ああ、とても素直な言葉だなと思いました。でも、そういうことですよね。
藤田:そう! ほんとにそう思う。反対に、忙しくてお昼を適当なものですませたりすると、夜ガツガツ食べて、「ああなんかすごくひもじかったんだな」って思う。
明子:満たされてない分を、穴うめしようとしちゃうんですかね。
藤田:そう、だからそこはお酒もちゃんと満たされるような酒質のものを飲まないと。お酒も「ああ美味しい」って感動しないと、飲んだ気しない。だから第1回の有末さんと山根社長の対談「淫美な酒」を読んで思いましたが、いいお酒って、もう他のことはどうでもよくなっちゃうのがいいお酒だと思うんですよね。酒でもほかのことでもなんでも。あとのことはもうどうでもいいって思えるくらいのことじゃないと、面白くないし、飲まなくていい。そこそこのものしかないって面白くない。金のあるなし関係なしに(笑)

